愴海《うみ》に眠れ(中編) 遠雲《ユンワン》
チベ級重巡洋艦を旗艦とする五隻のジオン艦隊の行方が四時間にも渡って、不明になっていたのには理由がある。
ウォルドロン隊の十一隻の突撃艇が決死の攻撃を敢行した際、ジオン艦隊は明らかに基地のある小惑星に向けての進路を取っていた。そして、ウォルドロン隊の壊滅によって、触接が絶たれた後も、司令部では五隻は基地に向かっているものと考えて、捜索を行っていた。
しかし、実際にジオン艦隊が発見されたのは小惑星『ルナツー』を地球側に大きく迂回した地点だったのである。
それが何を意味するのか。
司令部の思い当たった答えは一つだった。
実はこの日、南アジアの宇宙港から物資を満載した輸送船団が小惑星へと向かっていた。
この輸送船団を出迎えるべく、八隻のサラミス級巡洋艦が基地を出発し、ランデブー・ポイントで待機していた。
「まずいな。」
敵にチベ級重巡洋艦がいても、隻数が三つ多い分、砲戦能力は優位と判断されたが、モビルスーツを保有している分だけ、総合的に敵が優位だった。
さらに、サラミス級巡洋艦はたとえ一隻といえども、今の地球連邦軍にとって失うことの許されない貴重な戦力であった。
だが、手立てはある。
敵の進路は今や、ほぼ完全に予測できていた。
輸送船はもちろん、八隻のサラミス級巡洋艦にも一時的な退避針路を取らせ、発生するであろう決戦の時期を遅らせる。
そうして、稼いだ時間によって小惑星から増援の突撃艇部隊を送り込み、十分な戦力的優位を保った上で一気に殲滅すればよかった。
さらに八隻の巡洋艦とマゼラン級戦艦を出撃させるべきという意見も一部の参謀の中にはあったが、それは却下された。小惑星の防衛をがら空きにする危険をワッケイン司令官が避けたからである。
かくして、巡洋艦と輸送船には一時的な退避命令が下された。
そして、突撃艇部隊には巡洋艦と合同するべく、命令が下されたのである。
ただ、壊滅状態の第八雷撃隊にまで命令が下されたかどうかは定かではない。
キーリング大尉が無理に出撃許可を取りつけたともいわれている。
★ ☆ ★ ☆ ★
第八雷撃隊のブリーフィング・ルームには十五組七十五名のクルーを収容する容量がある。だが、この時の室内はこれまでの、どのブリーフィングよりも人が疎らだった。座る主のない椅子と触れる者のない端末機の接続ジャックが今はもう、いなくなってしまった人々のことを嫌でも思い出させた。
スノーは思う。
いつか、俺の座っているこの椅子も、俺を失って、新しい主を待つ時が来るのだろう、と。
隣に座るローラに気付かれぬよう、そっと預かったばかりのペンダントに触れる。
ローラの父は都会の学校に行く娘の無事を祈って、彼女に手作りのペンダントを与えた。
悲しい時は自分を思い出して、勇気を出してほしい。どんなことがあっても、決して自暴自棄にはならないでほしい。
都会に旅立つ娘に、父は語り尽くせぬ思いをペンダントに秘めたのだろう。
父が戦禍で死に、学校を休学して軍に志願、突撃艇の副操縦士になった今もローラは大切にペンダントを持っている。
彼女にとって、ペンダントは父なのだ。
ローラの父のように、俺は誰かに思い出してもらえるのだろうか。
少なくとも、この椅子は次の座り手に俺の思い出を語りはすまい。
死にたくはない。
人の存在は結局、他人の記憶によってでしか証明されないのだ。
俺の存在を証明してくれる誰かは……いやしない。
壇上にキーリングが上がった。
「諸君、早くもウォルドロン隊長ら戦死した仲間の仇を討つ時が来た!」
俺は仇討ちに来ているんじゃないぜ。
そんな囁き声が後ろの席から聞こえる。
見渡せば、どの仲間も、『タンガロア』のクルーと補充クルー以外は先刻の出撃で疲れきった顔を隠せずにいる。
無理もない。
雷撃を二度やった者はいない、と言われるほど、対艦攻撃は危険な任務なのだ。
キーリングは囁き声には気付かず、モニターに敵の航路図を表示させた。
「敵艦隊はルナツーを避け、地球からの輸送船団に向かっている。我々の任務は待機中の護衛艦隊と合流し、絶対の優勢を維持して敵を攻撃することである!」
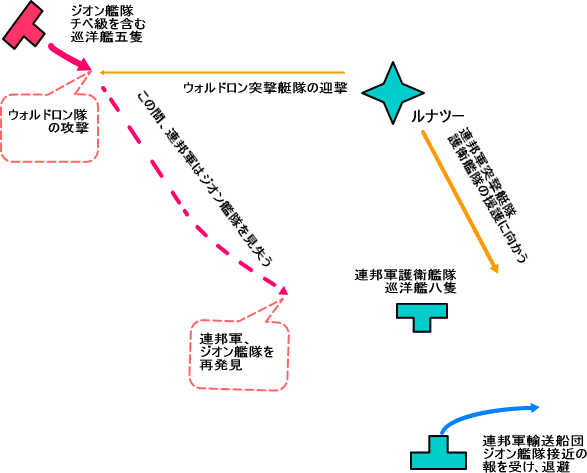
「使える艇は全部出す。マオ中尉の艇には補充クルーのスターリング中尉の組が乗れ。後の四隻は通常通りの搭乗割だ。いいな!」
スノーは愕然と顔を上げた。
五隻、全力出動とは聞いていない。精々『タンガロア』と状態の比較的良い二隻ほどが出撃すると考えていたのだ。
「大尉! 無理です!」
思わず声が出る。
キーリングは露骨に嫌な顔をした。元々、人前での反対意見を侮辱と取りかねない男である。しかも、言っているのが自分の部下なら不機嫌も増すのが当然だった。
「何が無理だ、シュネーヴァイス。」
スノーは答えなかった。代わりに後ろを振り向き、最後列で控えめに座るメカニックマン達に声をかける。
「全艇修理完了しているのか。」
五人ほど代表して参加しているメカニックマンは互いに顔を見合わせた。だが、誰もがキーリングの逆鱗に触れるのを怖れて発言しない。
「どうなんだ!」
スノーが声を荒げる。その様子を苦々しげにキーリングが睨んだ。
スノー……、と隣の席のローラがスノーの袖を引っ張る。だが、スノーはそれを無視した。
やがて、意を決したように縮れ髪の一人の下士官が立ち上がった。
「ロウ中尉艇ニューオーリンズ・ラブ付のオムル曹長であります。第三バーニアが破損しており、瞬間加速力が通常の七十五パーセント以下に落ちる他、姿勢制御にも問題が出ております。」
スノーはチラリと自分の右前に座るロウ中尉の顔を見た。
青いノーマルスーツに、外したヘルメットの代わりに軍帽を目深に被った中尉は腕を組んだまま、目を閉じている。
対照的に中尉のクルーは心配げにオムルとキーリングを見比べていた。
「また、燃料タンクにも七十センチの亀裂があり、応急処置は施しておりますが……。」
「何故、直しておかないのか!!」
キーリングが演壇を叩いて怒鳴り声を上げた。
「ですから、それは先ほど報告を……」
オムル曹長の弁解をキーリングは聞こうとしなかった。彼は演壇の床を蹴ってオムルの前までジャンプするや、いきなりオムルの下腹を蹴り上げた。
吹っ飛ばされて、壁に激突したオムルを他のメカニックマン達が助け起こす。
「艇長、二時間では無理な修理です。」
『タンガロア』の機関士ハンク軍曹が立ち上がり、同じ整備科の人間としてオムル曹長を弁護に入る。
キーリングの顔が醜く歪み、ハンクに対しては不気味な薄笑いを浮かべた。
俺に逆らったな、ハンク、目はそう語っている。
蛇に睨まれた蛙のようにハンクは竦み上がり、ローラやスノーに救いを求めるように哀願の目を向けた。
そんなハンクを無視したキーリングはオムルの縮れた髪を掴むや、その顔を身長二メートルの自分と同じ高さまで引き上げた。
「オムル曹長!」
「は……はい…。」
「貴様は義務を怠った! そうだな!」
「は…いえ……は……。」
「銃殺だぞ! オムル二等兵!!」
スノー! ローラが隣で囁く。
意を決してスノーが立ち上がった時だった。
「よしましょうや、こんなところで!」
濁声《だみごえ》が室内に響いた。
ロウ中尉であった。
彼は軍帽を被ったまま、片手で金髪をかき上げ、涙目になって震えているオムル曹長に微笑みかけた。
「心配いらねえよ、ちゃんと出撃して、ちゃんと戻ってくるって。」
文句ないでしょ、隊長代行、と「代行」の部分に力を入れて、ロウは初めてキーリングの方を向いて言った。
やや気圧されたキーリングは「ああ、まぁ、な。」と声を落として答える。
「それじゃ、これで万事よし、と!」
彼は、そう言うと同時に自分のクルー達に向き直り、彼の背中を叩いた。
「ほらほら、シケた面してんじゃないよ。仕事だよ、お仕事!」
そう言いながら、「代行!ブリーフィングの続きどうしたの!」とキーリングを呼ぶ。
キーリングは舌打ちして、再び壇上に向けて床を蹴った。
「死ぬ気だよ……あの人…。」
再び後ろの席で誰かが囁いた。
スノーは静かにロウを見つめた。
![]()
基地に驚くべき報告が入電したのは突撃艇部隊が飛び立ってから一時間以上も過ぎてからである。
巡洋艦部隊大敗の悲報だった。
三隻が轟沈、一隻が大破して艦隊を脱落、残る四隻は算を乱して避退中だという。
司令部の出した一時退避命令はどういう事情からか、巡洋艦部隊の司令には届かなかったのだ。
巡洋艦部隊はそのまま輸送船団とのランデブー・ポイントに向かい、ジオン艦隊と遭遇、砲撃戦に入って壊滅の憂き目に遭ったのだという。
「モビルスーツにではなく、砲撃戦で壊滅させられたというのか!」
ワッケイン司令官が声を荒げた。
「チベ級一隻を含んでいるとはいえ、五対八だぞ!」
そ、それが閣下…、と作戦参謀が蒼い顔のまま、答える。
「敵艦五隻は全艦サラミスの有効射程の外から発砲してきたと…。」
「馬鹿な! チベはともかく、ムサイ級巡洋艦の有効射程はサラミスに劣るはずだ。」
「ムサイではない可能性が…。」
「グスマン級か!」
ワッケインは呻き、参謀は悲痛な面持ちで頷いた。
グスマン級巡洋艦は外見上はムサイ級巡洋艦に酷似しており、最初に攻撃した突撃艇クルーが見誤っても不思議はない。しかし、その砲戦能力、特に有効射程では準同型のムサイ級を遥かに凌駕していると伝えられていた。情報ではグスマン、ボリバル、ナセル、アラファトの四艦が就航しており、この戦隊とチベ級巡洋艦が五隻で打撃部隊を構成していることは想像がついた。
「閣下、このままでは後続した突撃艇隊も…、いや、輸送船団も…。」
「船団をやらせるわけにはいかん!」
ワッケインは叫んだ。
「あの船団には新型モビルスーツの組み立てに必要な資材と人員を積んでいるのだ。それと新型宇宙戦闘機とメカニック達もだ。」
反攻作戦にはなくてはならない輸送船団なのだ。
ワッケインは呟いて唇を噛んだ。
「突撃艇隊と連絡は取れないな。」
「無理です。あの宙域はミノフスキー粒子の濃度が濃すぎて。」
通信参謀が無念やる方ない面持ちで答えた。
「基地の全艦艇を出撃させろ。マゼラン級戦艦の出撃も許可する。半分でもいいから輸送船団を守れ!」
ワッケインはそう言って、右手の親指と人差し指で上唇を押さえた。
駄目かもしれん…そう言いたいのを彼はじっと堪えた。
★ ☆ ★ ☆ ★
遥か遠くに別の雷撃隊のバーニア炎が光る。
その向こうでは地球が青く輝いていた。
五隻の突撃艇は斜めに編隊を組んで宇宙空間を進んでいた。
旧世紀のスペースシャトルに似た胴体には『フィッシュ』とクルー達に渾名される大型の対艦用ミサイルが二発、しっかりと抱きかかえられている。
その姿が旧世紀の雷撃機を思わせることから、彼らは雷撃隊と呼ばれる。
だが、既にその時代から「雷撃を二度やった者はいない」とも言われていた。
魚雷命中のために一定距離の直進を必要とするため、撃墜される確率が極めて高いからである。
第八雷撃隊はこの日だけで、二度目の『雷撃』に出撃していた。
先頭を行くのは『タンガロア』号である。
鯨のアートが後続する寮艇『ピンク・バッカニア』のピンクの帽子を被った海賊を見つめているように見えた。
「見事に隊長の仇を撃てば、勲章は間違いなしだぞ。ハンク軍曹!」
いつのまにか上機嫌になっているキーリングの与太を聞いて、スノーとローラは顔を顰《しか》めた。つい今し方、彼はハンクの顔を形が変わるほど殴りつけたばかりだったのだ。
「俺が隊の指揮を采っている以上、何の心配もいらん。貴様は無事に帰って勲章を受けられるぞ、ハンク軍曹!」
何故、自分が指揮を采っているから大丈夫なのか。彼がこれまで出撃を嫌がってきたのはウォルドロンの指揮が良くなかったからだとでも言うのか。
操縦席の背後から聞こえてくるだけでも、不機嫌になってくる与太にスノーは文句を言おうとしたが、またもローラがそれを止めた。
「あいつ…殺してやる…。」
「スノー!」
小声で話す二人の会話はキーリングには聞こえていない。
「キム、僚艇は遅れてない?」
「通信室から副操縦士へ、四隻の後続を確認。」
何とか、付いてきてるようですね、とローラがスノーに言った。
「ロウ中尉、何であんなことを言ったのかしら。出撃拒否はできたはずなのに。」
オムルを救うためとはいえ、腑に落ちない、といった風にローラはスノーに尋ねた。
「軍人だからだよ。」
スノーは前の宇宙空間を見つめながら答える。
「士官学校の生徒は十代の時から命令に従うことだけを教えられるんだ。」
ロウ中尉だって、あれが精々なんだよ。
スノーは少し遠くを見るような目をした。俺は軍人になって本当に良かったのかな、目はそう語っていた。少なくともローラにはそう見えた。
「スノーもそうなのかしら?」
「俺は劣等生なの。」
そう言って、口を尖らせるスノーにローラは吹き出した。
「良かった。」
「何が?」
「元のシュネーヴァイス少尉の顔に会えました!」
何を言ってるんだか、とスノーは呟く。そういうスノーを見て、ローラはまた笑った。
「ウィピティ軍曹! 何を笑うか! 不謹慎だぞ!」
後ろの航法士席で二人を見咎めたキーリングが怒鳴った。
申し訳ありません! と言葉を返しながら、ローラはスノーにだけ解るように中指を立てた。それを見たスノーも漸く微笑んだ。
通信室のキムが突然、声を張り上げたのはその時である。
「第六雷撃隊より連絡! 敵モビルスーツ隊の攻撃を受けています!」
コクピット中の空気が凍りついた気がした。
![]()
「第六雷撃隊からのレーザー通信を受信しました。」
敵モビルスーツ六機の迎撃を受けています、と通信参謀がワッケインに報告した。
作戦室の全員が嘆息した。
事態はどんどん悪化している。
避退するサラミスを追ったジオン艦隊は連邦軍突撃艇隊の予定進路上に進出してしまったのだ。
突撃艇部隊はまず、サラミス部隊に合流してから、攻撃に向かう予定だったが、突然、敵の迎撃機に襲われる形となってしまった。
「搭載数から計算すると、後十六機のモビルスーツがいることになるが……。」
情報参謀が不安げに呟く。それだけのモビルスーツが繰り出されれば、突撃艇隊も間違いなく壊滅してしまうだろう。
いや、と若い尉官参謀が情報参謀の方を向いた。
「そんなにいれば、サラミス部隊の追撃にモビルスーツを使っていてもおかしくありません。迎撃機としてのみ使用していることを考えると、いても後三機、予備機を合わせても六機というところでしょう。」
地球侵攻以来、ジオンのモビルスーツは不足していますから、と尉官参謀は説明した。
「第六雷撃隊はミサイルの投棄を行った模様。」
通信参謀が第二報を入れる。
「腰抜けめ!」
そう毒づくの作戦参謀である。いや、いいんです、と先ほどの尉官参謀が反論した。
「第六雷撃隊は十二隻で出撃しています。敵の迎撃機はモビルスーツが六機ですから、十二隻がミサイルを投棄して敵迎撃機の攪乱に回れば、後続の雷撃隊が敵艦隊に突っ込むことが容易になります。」
「第三雷撃隊と第八雷撃隊が第六雷撃隊に後続して突入します。」
さらに別の士官が尉官参謀の言葉を継いだ。
「五月雨突入にならねばいいが、第六が追い散らされた後で突入しても、カモになるだけだぞ。」
毒づいた参謀が尚も、不満げに懸念を表明する。
「こちらからの命令が届かないのです。彼らはまず、巡洋艦と合流してから攻撃するつもりでしたから、こんなところで敵と遭遇するとは予想していなかったはずです。」
「第三と第八は何隻で出たんだ。」
初めてワッケインが口を挟んだ。
「合わせて十三隻です。第八の損傷艇も含めて全力です。」
少なすぎる…またもワッケインは呻いた。
★ ☆ ★ ☆ ★
申し合わせたわけでもなく、スノーとローラは同時にヘルメットのバイザーを閉じた。
彼方に巡洋艦のバーニア炎が確認できる。
攻撃目標であった。
そして、巡洋艦と『タンガロア』の間の空間では第三雷撃隊の八隻のバーニア炎が先行して進んでいる。さらにやや離れた宙域で第六雷撃隊が敵の迎撃部隊を攪乱している。
「突撃準備隊形用意!」
キーリングが号令した。お馴染みの号令だったが、その後の言葉がスノーを仰天させた。
「二列縦陣を組む! 第一列先頭艇はニューオーリンズ・ラブ、ピンク・バッカニアが後続、最後尾がタンガロア! 第二列は第一列の左舷に展開!」
攻撃は横陣か、同時多方向攻撃がセオリーとされていた。縦陣、つまり敵に向かって、真直ぐ並ぶ隊形は突撃艇では時代遅れとされている。しかも、先頭艇は指揮艇が務めるのが原則だった。
思わず耳を疑う。スノーとローラは顔を見合わせたが、キーリングの意図することを理解するや、スノーの背中に冷たい汗が流れた。
「艇長! 異議を申し立てます!」
「却下する!」
「仲間を盾にする気ですか!」
「指揮官は最後まで指揮を采らねばならんだろうが!」
「絶対、間違ってる!」
スノーは激昂していた。ローラも愕然として、スノーを止めるどころではなかった。
キーリングが自分が指揮を采るからには大丈夫、と言ったのはこういうことだったのだ。
眼前では先に突入を開始した第三雷撃隊の突撃艇に対して、ジオン艦隊がビームの光を放っていた。
「おい、スノー!」
電波通信でスノーのレシーバーに直接、語りかけてきたのは先頭艇を命じられた『ニューオーリンズ・ラブ』のロウ中尉であった。
「お前はまた、こんな時にゴチャゴチャ言うんじゃないよ!」
「中尉!」
「ニューオーリンズ・ラブ、命令を受領した。ピンク・バッカニア、遅れんなよ! 目標の選択は任せてもらうぜ。」
「中尉!」
「なあ、スノー、悲しいけど、これ、戦争なのよね!」
「中尉…。」
「それから、キーリング大尉!」
無線で名前を呼ぶな! とキーリングは怒鳴ったが、ロウは構わなかった。
「あんた、世界一のクソったれだぜ!」
キーリングがまた怒鳴ったが、ロウはもう返事をしなかった。
![]()
『上官拘束事件』の真相が愈々、明らかになりつつあります。皆さん、目が放せませんよ☆
な、遠雲さんのゲスト作・第2弾です。更にハードに展開中。スノーが切れそうで踏み止まってますが、さて、どうなりますやら^^;
オマケに、大サービス満載で、チラホラとどこかで聞いたことのあるような名前も? さて、彼らは何者なのでしょうか?? それは後編のお楽しみ♪
『刮目して、待てっ☆』(Gロボ風に?)
2004.04.13.
![]()